はじめに
競争に勝ち抜く、住宅業界のブランディング戦略
近年、分譲住宅業界はこれまでにない大きな転換期を迎えています。立地や価格といった従来の勝ち筋が通用しにくくなり、顧客の価値観が急速に多様化・高度化するなかで、住宅そのものが持つ「選ばれる理由」がますます重要になっています。
『分譲住宅ブランディング戦略』は、こうした時代背景を踏まえ、住宅を“売る”のではなく“選ばれる”状態をつくるための実践的なアプローチをまとめた一冊です。
本書評では、分譲住宅の未来に向けて本書がどのような気づきを与えてくれるのかを、実務目線で紐解いていきます。
著者紹介
奥村友裕(おくむら ともひろ)
1976年大阪市生まれ。大学院で経営学を専攻後、大手コンサルティング会社にて部長職を歴任。論理的な問題解決が求められる業界において、「感性と論理」を融合させた独自アプローチで高く評価される。2017年に株式会社クラフトアールを設立し、「美意識を大切にする経営改革プロ集団」として多様な企業のブランディングと経営支援を行う。2023年には分譲住宅業界の未来を見据え、株式会社戸建分譲総研を設立。住宅ブランディングの実践者として、土地仕入れ・商品企画・営業・マーケティングの全工程に携わりながら、全国の分譲住宅事業の支援と再構築に尽力している。教育事業にも注力し、未来のリーダー育成にも取り組んでいる。
1. 「建てて売る」から「選ばれる」へ
── 分譲住宅の価値観が大きく変わり始めた理由とは

1-1. 「選ばれる家」とは、価格だけでは決まらない時代へ
分譲住宅のビジネスが、静かにその姿を変えようとしています。
かつては「立地さえよければ」「価格が安ければ」売れた時代。しかし今、その成功法則は通用しなくなりつつあります。
大手ハウスメーカーの本格参入、そしてパワービルダーの急成長。市場の選択肢は増え、顧客の目も肥えてきました。
分譲住宅であっても、“注文住宅と同じ熱量”で選ばれる理由を持っていなければ、選ばれる側にはなれない。そんな時代が到来しています。
では、いかにして顧客の心を動かし、競合から抜け出すか? そのヒントを凝縮した一冊が『分譲住宅ブランディング戦略』(奥村友裕 著)です。
1-2. 注文住宅よりも、分譲住宅の方が「ブランド」が武器になる
分譲住宅と注文住宅の違いは、「選ばれ方」にあります。
注文住宅は顧客の要望に応えて“つくっていく”家。一方で分譲住宅は、すでにできあがったものを“選んでもらう”家です。
だからこそ、商品そのものの「見せ方」「語り方」「伝え方」が極めて重要になります。
本書では、そうした分譲住宅ならではの“選ばせる力”を育てるために、以下の3つの視点からブランディング戦略を分解しています。
- デザイン戦略(直感で「住みたい」と思わせる外観・街並み)
- セールス戦略(顧客の決断を導く営業のプロセス)
- マーケティング戦略(住宅の価値を届けるための情報設計)
この3軸を貫く思想が、「分譲住宅=建物」ではなく、「分譲住宅=顧客体験」というアプローチです。
建てることに注力してきた業界が、今こそ「選ばれること」に意識をシフトするべき時なのです。
1-3. 顧客の“感情”を動かすことが、これからの差別化
「良い住宅は売れる」──この言葉が成り立たなくなってきたのが、今の分譲住宅市場です。
顧客は“比較しやすくなった”からこそ、物件の優劣ではなく「どれに感情が動いたか」で決断する傾向が強まっています。
つまり、「見た目」「ストーリー」「信頼感」。この3つを高いレベルで構築できるブランドだけが、選ばれていく。 本書では、そんな時代に必要な視点を、事例や考察を交えながら非常にわかりやすく提示してくれます。理論一辺倒でもなく、情緒的すぎることもない。
現場の営業担当者から、事業戦略を描く経営層まで、それぞれの立場で“明日から使える気づき”が詰まっています。
1-4. この本は、こんな方におすすめです
- 「価格を下げる」以外の武器が見つからないと感じているデベロッパーの経営者
- 営業活動が思うように成果につながらず、悩んでいる責任者
- 自社の分譲住宅に“らしさ”がないと感じている企画・設計担当者
- 注文住宅とは異なる戦略が必要だと感じながら、方向性に迷っているマーケター
どれかひとつでも当てはまるなら、本書を読む価値は大いにあるはずです。
そして、分譲住宅ビジネスにおける「ブランドづくり」は、きっと今後の企業成長の鍵になる──そんな確信を持たせてくれる一冊です。
2. なぜ、分譲住宅は“選ばれなくなってきた”のか?
── 業界全体が直面する「構造的な課題」とは

2-1. 土地を押さえれば売れた時代は、もう終わった
ひと昔前、分譲住宅ビジネスにおいて成功の鍵といえば「好立地の仕入れ」でした。
住宅性能や外観の違いはあれど、需要があるエリアに建てさえすれば“売れた”。そんな時代が確かに存在しました。
しかし現在は、土地の価値だけでは戦えません。どれだけ駅近・商業施設近くの物件であっても、顧客は慎重に比較・検討を重ねます。
競合の選択肢が無数にある今、住宅の“中身”そのものの魅力が問われる時代になっているのです。
2-2. パワービルダーの急拡大が、顧客の価値観を変えた
近年、分譲住宅市場の風景を一変させた存在が「パワービルダー」です。
価格を抑えながらもデザイン性や機能性に優れた住宅を、短期間で大量に供給するその手法は、多くの若年層に支持されてきました。
結果として、「住宅の見た目やブランドにこだわるのは一部の富裕層だけ」という過去の認識は完全に崩壊。
今や20〜30代の若い購入層でさえ、「せっかく買うなら、雰囲気も妥協したくない」と考えるようになっているのです。
2-3. 価格だけでは選ばれない。けれど、何で差をつける?
価格競争に巻き込まれないために、多少なりとも高単価な分譲住宅を提供しよう──。
そう考えている企業は少なくありませんが、「高い分、何がいいのか?」を説明できないケースも多く見られます。
営業現場でも、「価格は安くない。でも良い家です」としか言えない状況。
Webサイトでも、「安心・快適・こだわり」などの抽象的な言葉しか並んでいない状態──。
顧客が“選ぶ理由”を見失っているのは、実は事業者側が“伝える言葉”を持っていないからかもしれません。
2-4. ブランド力は「後付け」ではなく「設計段階」で決まる
分譲住宅における“ブランド”は、ロゴやコンセプトを打ち出すことではありません。
設計、デザイン、販売のすべての段階において、「誰に・なぜ・どのような暮らしを提供したいか」が一貫しているかどうか。そこに尽きます。
本書『分譲住宅ブランディング戦略』が強調するのは、まさにその“本質”です。
選ばれる分譲住宅には、価格でもスペックでも測れない「選ばれる理由」がある。
それを設計の根幹からつくっていく視点が、これからの分譲住宅には不可欠なのです。
3. ブランドとは、「売り文句」ではなく「設計思想」である
── 『分譲住宅ブランディング戦略』が提示する、逆転のアプローチ

3-1. 「なぜこの家が選ばれるのか?」に、明確な答えはあるか
競合との差を生みたい。価格ではなく価値で勝負したい。
そう考えてはいるものの、「この分譲住宅が選ばれる理由は?」と問われたときに、即答できる担当者がどれだけいるでしょうか。
「立地がいいから」「設備が最新だから」──それは“違い”ではあるかもしれません。
でも“選ばれる理由”にはなり得ません。なぜならそれらは、他社も簡単に再現できるからです。
本書『分譲住宅ブランディング戦略』は、この“根本的な問い”に立ち返ることから始まります。
分譲住宅を建てるとき、売るとき、届けるとき──それぞれの工程において、「ブランド」という視点をどう織り込んでいくか?
その設計思想こそが、競争優位をつくるのだと、本書は静かに、しかし確かに語りかけてきます。
3-2. 感情を動かす家は、理屈ではなく“設計”から生まれる
人が住宅を選ぶとき、すべてを合理的に判断するわけではありません。
「なんとなく、ここが良い気がする」「この街並みに惹かれた」──こうした“感覚”が、最終的な意思決定に影響を与えます。
だからこそ、今の分譲住宅に必要なのは、「スペックを上回る感情設計」なのです。
本書ではこの“感情を動かす仕掛け”を、デザイン・営業・マーケティングの3つの視点から紐解いていきます。
- デザインは、直感的に「住みたい」と思わせる外観や街並みをつくること
- 営業は、「この家が自分に合っている」と顧客に納得させる導線を描くこと
- マーケティングは、「この家でどんな暮らしができるか」を想像させる情報発信を担うこと
この3つがバラバラに動いていては、ブランドは一貫性を持てません。
むしろ、それぞれが同じビジョンを共有し、ひとつの“顧客体験”をつくるという認識が必要なのです。
3-3. 部署をまたいで一貫した「ブランドの軸」を持てているか?
分譲住宅の多くは、設計担当者、営業、販促担当、広告代理店と、複数の関係者が連携してつくりあげています。
それぞれがプロフェッショナルである一方、時として「なぜこの家を売るのか」「誰に届けたいのか」がズレたまま、プロジェクトが進行してしまうことも少なくありません。
本書が提案するのは、この“バラバラ”を“統合”へと導くアプローチです。
例えば──
「この分譲住宅は、共働きで子育て中の30代夫婦が、仕事と育児のバランスを取りながら暮らせる家だ」と明確に定義したとき、どうなるか?
- 設計は、「時短動線」や「在宅ワーク対応」など、暮らしに即した間取りを生み出す
- デザインは、柔らかさや安心感を演出し、自然と顧客にフィットする世界観を醸成する
- 営業は、そのライフスタイルに合わせた提案ができ、「自分たちにぴったり」と思わせられる
- WEBサイトや広告は、「共働き家族の理想の暮らし」という物語を一貫して発信できる
このように、“住む人の姿”を軸にしたブランド設計があることで、すべての工程にブレがなくなり、住宅の魅力が“言葉”でも“ビジュアル”でも、自然に伝わっていくのです。
3-4.「売る」ではなく、「選ばせる」へ。営業のあり方も変わる
営業の現場では、つい「どうやって決断させるか」を考えがちです。
でも、これからの営業に必要なのは、「どうやって顧客が自分で選びたくなる状況を設計するか」という発想です。
- 顧客が無理なく比較できる資料設計
- 過剰な情報提示ではなく、選択肢を絞った案内
- 「買う理由」ではなく「暮らしたい理由」に焦点を当てたプレゼン
こうした“営業プロセスの再設計”もまた、ブランドづくりの一環であると本書は指摘します。
単に物件を紹介するのではなく、「この家を選ぶ自分」に納得してもらうこと。それこそが、分譲住宅における営業の本質なのです。
4. 「建てて売る」から、「暮らしを選ばせる」へ
── 本書が与えてくれる3つの実践的ヒント

1|感性に訴えるデザインで、無意識の「ここに住みたい」を引き出す
分譲住宅の購入を検討している顧客が、最初に出会うのは“スペック”ではなく“印象”です。
外観や街並みのトーン、敷地全体の統一感、植栽や照明など、パッと見て心が動くかどうか。それがファーストインプレッションのすべてを決めます。
本書では、その第一印象をいかに「直感的に住みたくさせるか」を明確な戦略として定義しています。
特に印象的だったのは、“一棟ごとのデザイン”ではなく、“街区全体としてのブランディング”の重要性。
外観デザイン、門扉やフェンスの選定、分譲地の構成、色彩のバランス──
それらの総合的な美しさが、顧客のWTP(Willing To Pay:支払意思額)を底上げする力になるという指摘には、大きな納得感があります。
分譲住宅でも、「この街に住んでいる自分が好きになれそう」と思わせること。
それこそが、価格ではない価値で選ばれるためのスタートラインです。
2|セールスは“提案”ではなく“編集”。情報を削る勇気が信頼を生む
営業の現場でありがちなのが、「とにかく多くの物件を見せる」スタイルです。
しかし本書では、それが“買えない顧客”を生み出してしまう要因になると明確に指摘されています。
選択肢が多すぎると、顧客は迷い、判断を保留にしてしまう。
だからこそ、セールスは「何を伝えるか」よりも「何を省くか」を戦略的に考える必要があるのです。
そのために必要なのが、以下の3ステップ:
- 信頼構築:売り手としてではなく、“住まい選びの伴走者”として顧客と関係を築く
- フレーミング:価格や仕様ではなく、“暮らしのイメージ”で価値を提示する
- 差別化:他物件との違いではなく、「なぜこの人にとって合っているのか」を言語化する
これらの思考法をインストールすることで、「買ってもらう」営業から「選びたくなる」営業へと転換が図れます。
本書では、その実践に必要な言葉の使い方、資料設計の視点まで丁寧に触れられており、営業担当者は必読の内容です。
3|住宅は「商品」ではなく「物語」。マーケティングにストーリーを
分譲住宅を“商品”として見せるだけでは、心に残りません。
性能・価格・間取り──そのどれもが重要ではあるものの、「そこに暮らす未来」が描けない限り、顧客の心をつかむことはできないのです。
本書では、マーケティングの役割を「スペック紹介」から「ストーリー設計」へと大きく転換する必要性を語ります。
たとえば、以下のようなアプローチ:
- ペルソナに共感を呼ぶキャッチコピー:「夫婦ふたり、働きながら“余白”も楽しむ家」など、生活像を描く言葉選び
- ブランディングムービーやSNS活用:家の“仕様”ではなく、“そこで暮らす人”を主役にしたビジュアルコミュニケーション
- 予約状況や分譲エリアの価値を発信するWEBサイト設計:希少性とタイミングの演出による“今買いたい”気持ちの喚起
これらの施策によって、分譲住宅が「ただの商品」から「選ばれる暮らし」へと昇華します。
本書が教えてくれるのは、「仕組みのデザイン」で売れる状態をつくること
『分譲住宅ブランディング戦略』が提示するのは、個々のテクニックではありません。
あくまで、住宅をどう見せ、どう語り、どう届けるかという“仕組みそのもの”を再設計する視点です。
- 顧客にとって“暮らしの理想”を体現したような外観・設計
- 自然と決断したくなる導線設計と営業アプローチ
- 物件そのもののスペックではなく、暮らしを語るストーリー
これらを通して、「建てたあとに売る」のではなく、「売れる状態で建てる」ことが可能になる。
その実践へのヒントが、随所にちりばめられている一冊です。
5. 選ばれる家には、理由がある
── 「ブランドで売る」時代の分譲住宅づくりへ

5-1. 「売る家づくり」から、「選ばれる家づくり」へ
分譲住宅は、これまで“合理的に建てて売る”ことが第一とされてきました。
しかし、いま顧客が求めているのは、「ここに住みたい」と心から思える“暮らし”です。
つまり、住宅そのものではなく、その背後にある世界観、生活の質、感情的な納得感──それらが意思決定の鍵になっています。
『分譲住宅ブランディング戦略』は、この市場の変化に対し、住宅事業者が取るべき“構造的な戦略転換”をわかりやすく示してくれる一冊です。
5-2. 本書が教えてくれる3つの本質
- 分譲住宅の価値は、価格や立地ではなく「物語」で決まる
- 営業の成果は、「情報量」ではなく「編集力」で決まる
- デザイン・営業・販促がバラバラでは、ブランドにはならない
これらは、単なるノウハウやテクニックではなく、“思考のフレーム”そのものをアップデートする視点です。
一度読み込んでおけば、自社の商品開発や販売戦略の見直しにもすぐ活かせるでしょう。
5-3. あなたの会社は、「選ばれる理由」を語れていますか?
- 「価格を下げる」以外の打ち手を探している
- 「差別化したつもり」でも、顧客に伝わっていない
- 「売る」だけでなく、顧客に「選ばせたい」
- 「営業」「設計」「販促」が、それぞれ別の言語で話している気がする
──そんな課題を感じているなら、本書があなたのビジネスの視野を広げてくれるはずです。
5-4. 建てる前に「売れる状態」をつくるために
住宅業界が直面する本質的な構造変化に対して、感覚論ではなく“理論と再現性”で応える。
そんな稀有な一冊が、この『分譲住宅ブランディング戦略』です。
分譲住宅ビジネスを進化させたいと願うすべての企業にとって、
「なぜ選ばれるのか?」という問いに向き合うための第一歩として、強くおすすめします。
6. 分譲住宅ブランディングの最前線を体感しよう
── 特別プレゼントキャンペーンのご案内
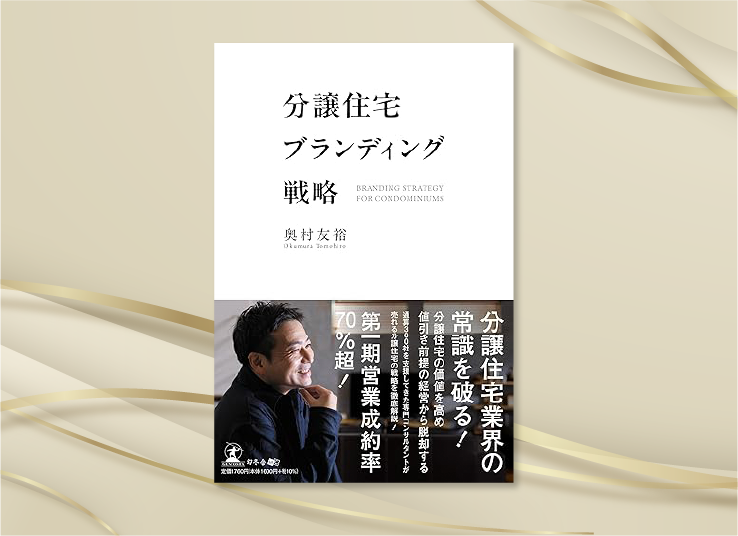
『分譲住宅ブランディング戦略』(奥村友裕 著)
分譲住宅に、ブランドという武器を。
住宅業界の“あたりまえ”を再定義する一冊。
特別プレゼントキャンペーン!
日頃Adransをご愛読いただいている皆様へ感謝を込めて――
先着20名様限定! 『分譲住宅ブランディング戦略』を無料でプレゼント!
業界必読の一冊を手に入れるチャンス!お早めにお申し込みください!
